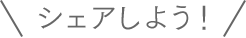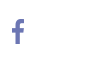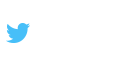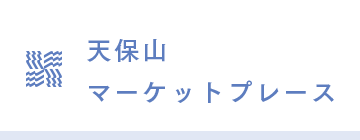どこまで増えるかな?(「日本の森」のテイカカズラ)
- 2023.05.13
- 魚類チームの日記
ここ数年、「日本の森」中央の擬木まわりに、つる植物のテイカカズラを展示しています。
(→「枯れ木に花を」)
今年も花が咲く時期になりました。
「日本の森」を見回すと、あちこちにテイカカズラが!
カワウソと水鳥の水槽の間にも 
オイカワのいる水槽の上にも 
竹藪の下にも 
そして水鳥の水槽の上にも!! 
あちこちに増えました。
さて、このテイカカズラの「テイカ」とは平安時代末期から鎌倉時代初期の歌人・藤原定家からきています。藤原定家といえば百人一首の撰者で、新古今和歌集などにも関わった歌人です。
百人一首の中にある定家の歌は
「来ぬ人を まつほの浦の夕凪に 焼くや藻塩の 身もこがれつつ」。
現代語訳では「いつまでたっても来ない人を待っています。松帆の浦の風が止まった夕方に海藻を焼いてつくる塩のように、私の身も恋い焦がれてながら」。
なお、松帆の浦とは淡路島の北の端にある松帆崎の海岸のことだそう。定家さんは関西にいらっしゃったのですね。って、この時代は京都がまつりごとの中心だったから当たり前か?
まあ、このように情熱的な歌を詠む定家さんの恋人は高貴な身分の方だったそうで、彼女が亡くなった後に忍んで葛(かずら)となり、墓に絡みついたというのが名前の由来。ちょっと怖くないですか??
花言葉も「優雅」とか「さわやかな笑顔」とかの他に「依存」ってあるし...。
茎から気根をだし、樹や岩にはりついていくからだと思いますが。しかし、岩や木の多い「日本の森」にはぴったりの植物ではあります。
この時期に咲く花の形はスクリューみたいでおもしろく、においもよいので、触らず、そっとご覧いただければと思います。
- カテゴリー
- 月別アーカイブ